 見ることについて気になっている。写真と絵画のちがいについて考える時、デビッド・ホックニーが始めた写真を部分で撮影してつなぎ合わせる手法を思い出した。写真によるキュビズムや、視点の動き、遠近法にも踏み込んで表現できたのは画家の視点、絵を描く視点があったからなのだと思う。気になって図書館でなつかしく画集を見ていると、ホックニーが写真的視点について研究している「秘密の技法」を知った。カメラ・オブスキュラや、カメラ・ルシーダ、レンズを利用して絵画を描いてきた歴史を研究した学術書だ。最近イギリスで開催されたA bigger picture という展覧会のカタログには大きなキャンバスいくつも繋げて野外で描くホックニーの姿と9台のモニターを繋げた画面に9台のカメラ映像として風景を描いている姿がある。カメラについての考察を進化させているように思う。日本への巡回展があれば、久しぶりにホックニーの絵と映像を見てみたい。
見ることについて気になっている。写真と絵画のちがいについて考える時、デビッド・ホックニーが始めた写真を部分で撮影してつなぎ合わせる手法を思い出した。写真によるキュビズムや、視点の動き、遠近法にも踏み込んで表現できたのは画家の視点、絵を描く視点があったからなのだと思う。気になって図書館でなつかしく画集を見ていると、ホックニーが写真的視点について研究している「秘密の技法」を知った。カメラ・オブスキュラや、カメラ・ルシーダ、レンズを利用して絵画を描いてきた歴史を研究した学術書だ。最近イギリスで開催されたA bigger picture という展覧会のカタログには大きなキャンバスいくつも繋げて野外で描くホックニーの姿と9台のモニターを繋げた画面に9台のカメラ映像として風景を描いている姿がある。カメラについての考察を進化させているように思う。日本への巡回展があれば、久しぶりにホックニーの絵と映像を見てみたい。
子供たちのための本棚
 いつの間にか小学生になる子供が絵本を読んでないことに気が付き、なんとなく寂しくなってしまいました。かつて通っていた保育園には保護者がプレゼントした本棚がありました。絵本棚が老朽化していたので、リニューアルを提案し、子供の卒園を間近に認められ、大急ぎで制作完成させました。子供の目線に見やすく本が並ぶ様に設計し、保護者のアンケート用のポストも内蔵させました。貸出しシステムを借りる視点に立って変更したところ、今まで少ししか借りられていなかった絵本が多くの子供達が借りるようになりました。絵本を読む時間は限られているわけではないのに小学生になるとだんだん読まなくなってしまいます。ちょっと怖くなったり、嬉しい気持ちになったりしている子供の姿を見て、自分にもそんな時間があったのかと思うのには、同じ絵本を親子2世代で楽しむようになってきたこともあるのだと思います。絵本に興味を持って読む時期は人生のなかでごくわずかな時間なのかもしれません。だからこそ、子供が絵本を読む機会の手伝いができたことが嬉しかったのです。
いつの間にか小学生になる子供が絵本を読んでないことに気が付き、なんとなく寂しくなってしまいました。かつて通っていた保育園には保護者がプレゼントした本棚がありました。絵本棚が老朽化していたので、リニューアルを提案し、子供の卒園を間近に認められ、大急ぎで制作完成させました。子供の目線に見やすく本が並ぶ様に設計し、保護者のアンケート用のポストも内蔵させました。貸出しシステムを借りる視点に立って変更したところ、今まで少ししか借りられていなかった絵本が多くの子供達が借りるようになりました。絵本を読む時間は限られているわけではないのに小学生になるとだんだん読まなくなってしまいます。ちょっと怖くなったり、嬉しい気持ちになったりしている子供の姿を見て、自分にもそんな時間があったのかと思うのには、同じ絵本を親子2世代で楽しむようになってきたこともあるのだと思います。絵本に興味を持って読む時期は人生のなかでごくわずかな時間なのかもしれません。だからこそ、子供が絵本を読む機会の手伝いができたことが嬉しかったのです。
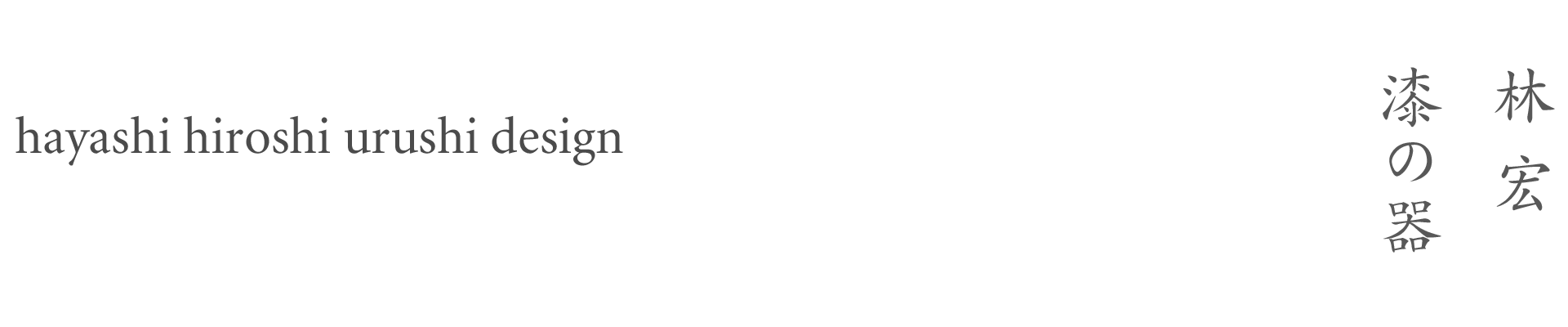


 家で飼っている2匹の猫は仕事部屋には完全入室禁止となっていて、事有るごとに隙あれば忍び込もうと、日々狙われています。絶対に入れないという心構えは出来ているつもりでも、その隙を見事について侵入するのが猫です。最初に入ったのは白い猫。漆刷毛を洗うための油壺の中に尻尾をしっかり浸してから脱出したようで、朝起きてみると廊下に見事な一筆書きが描かれていました。 油と漆が混じったドロドロのしっぽに困っている猫を丁寧に石鹸で洗い、なんとか事無きを得ました。
家で飼っている2匹の猫は仕事部屋には完全入室禁止となっていて、事有るごとに隙あれば忍び込もうと、日々狙われています。絶対に入れないという心構えは出来ているつもりでも、その隙を見事について侵入するのが猫です。最初に入ったのは白い猫。漆刷毛を洗うための油壺の中に尻尾をしっかり浸してから脱出したようで、朝起きてみると廊下に見事な一筆書きが描かれていました。 油と漆が混じったドロドロのしっぽに困っている猫を丁寧に石鹸で洗い、なんとか事無きを得ました。
 お箸に気を使っている人はいても、料理で使う菜箸にこだわりがあるという人は少ないのではないでいしょうか。中国で箸の調査する機会があり、工場で目にしたのは持ち手が錦色のよく見る竹の菜箸でした。全て日本向けに作られているという工場は、ウレタン塗料の匂いが充満する中、日本の漆器産地が書かれたダンボールの山に修められ、出荷の準備を待っていました。その光景を見て、すぐに菜箸を作るようにしました。料理のヘラも漆で使うヘラ木で作りました。消耗品だからこそ、少しずつ身体に取り入れている可能性もあるわけで、台所道具には心配りと、視線をむけてあげたいと思う。
お箸に気を使っている人はいても、料理で使う菜箸にこだわりがあるという人は少ないのではないでいしょうか。中国で箸の調査する機会があり、工場で目にしたのは持ち手が錦色のよく見る竹の菜箸でした。全て日本向けに作られているという工場は、ウレタン塗料の匂いが充満する中、日本の漆器産地が書かれたダンボールの山に修められ、出荷の準備を待っていました。その光景を見て、すぐに菜箸を作るようにしました。料理のヘラも漆で使うヘラ木で作りました。消耗品だからこそ、少しずつ身体に取り入れている可能性もあるわけで、台所道具には心配りと、視線をむけてあげたいと思う。 妻の製菓用、マトファーのパレットナイフが届いたので見てみると、持ち手の木部と金属部分とのコントラストがなかなか美しい。しかし手にしてみると持ち手は案外ザラザラとしていて、どうも持ち心地が悪いというので、サンドペーパーを掛け、漆を染み込ませ、溜塗りで仕上げると、それは手に吸い付くような感覚で、とても使いやすそうな道具になりました。ついでに金属のシフォンケーキヘラは型から外す時に金属同士こすれる音がするのが嫌だというので、専用のヘラも木で作り、漆で仕上げてみました。腕前はさておき、お互いにヘラがいかに大事かということや、やはり道具は美しくなくてはいけないということを確認しました。形から入るという言葉がありますが、道具の美しさにほれて、何かを始めるのも悪くはないことだと思います。
妻の製菓用、マトファーのパレットナイフが届いたので見てみると、持ち手の木部と金属部分とのコントラストがなかなか美しい。しかし手にしてみると持ち手は案外ザラザラとしていて、どうも持ち心地が悪いというので、サンドペーパーを掛け、漆を染み込ませ、溜塗りで仕上げると、それは手に吸い付くような感覚で、とても使いやすそうな道具になりました。ついでに金属のシフォンケーキヘラは型から外す時に金属同士こすれる音がするのが嫌だというので、専用のヘラも木で作り、漆で仕上げてみました。腕前はさておき、お互いにヘラがいかに大事かということや、やはり道具は美しくなくてはいけないということを確認しました。形から入るという言葉がありますが、道具の美しさにほれて、何かを始めるのも悪くはないことだと思います。




